| 健康維持や体質改善などを目的に保健機能食品(特定保健用食品・栄養機能食品)を利用している人は多いようですが、消費者の認識や利用実態は明らかではありません。
そこで、生活科学研究所では兵庫県消費者団体連絡協議会と共同でアンケート調査を実施しました。 (実施時期:平成16年8月、調査対象:兵庫県在住一般消費者1,289人) |
「健康食品」の定義が決められていなかったこともあり、厚生労働省は平成 13年4月、保健機能食品制度を発足させました。健康食品のうち、国が定めた安全性や有効性等の基準を満たしていれば「保健機能食品」と称することができ、 この「保健機能食品」はさらに「特定保健用食品」と「栄養機能食品」に区分されています。
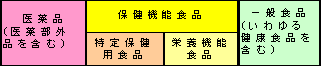
◆用途表示が認められている「特定保健用食品」
 「特定保健用食品」とは、健康の維持・増進や特定の保健の用途のために利用する食品です。国において、有効性や安全性などについての科学的根拠に関する審査を受け、許可された内容と右図のマークをつけ販売することができるものを指します。成分としては、オリゴ糖、乳酸菌、食物繊維、ペプチド、タンパク質、脂質、ミネラル等があり、食品としては、ヨーグルト、
サラダオイル、清涼飲料水、即席めん、クッキー、チョコレート、ガム等があります。
「特定保健用食品」とは、健康の維持・増進や特定の保健の用途のために利用する食品です。国において、有効性や安全性などについての科学的根拠に関する審査を受け、許可された内容と右図のマークをつけ販売することができるものを指します。成分としては、オリゴ糖、乳酸菌、食物繊維、ペプチド、タンパク質、脂質、ミネラル等があり、食品としては、ヨーグルト、
サラダオイル、清涼飲料水、即席めん、クッキー、チョコレート、ガム等があります。カルシウム、鉄、マグネシウムなど5種類のミネラル類とビタミンA、B1、B2、C、Eなど12種類のビタミン類があります。
これらの名称の周知度を調べたところ、「栄養補助食品」91.8%、「サプリメント」90.8%、「健康補助食品」77.2%に比べて「特定保健用食品」は61.8%、「栄養機能食品」は52.7%と低く、一般消費者に浸透しているとは言い難い状況でした。
◆約4割の人が特定保健用食品を利用
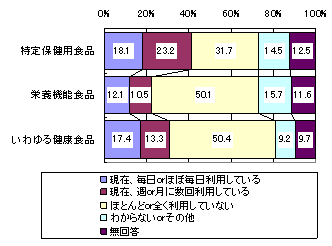
図1 保健機能食品の利用頻度(計=1,289人)
◆「特定保健用食品」に「効果があった」と答えた人は「いわゆる健康食品」より少なかった
しかし、利用した人に効果を尋ねたところ、「特定保健用食品」が、「効果があった」もしくは「少し効果があった」と考えている人は27.8%で、栄養機能食品:37.1%、いわゆる健康食品:31.1%に比べて少ないという結果でした。
その理由として、「特定保健用食品」は有効性が科学的に認められているため、宣伝の方法によっては、消費者が過剰な」期待を抱くことになり、実際にどの程度の効果が得られるのか、消費者に十分理解されていないことが考えられます。
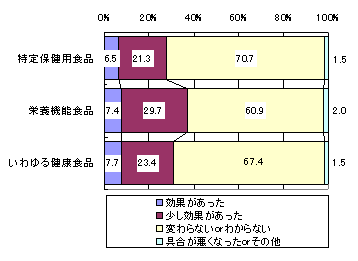
(特定保健用食品・計=738人、栄養機能食品・計=539人、いわゆる健康食・計=685人)
◆「特定保健用食品」では「おなかの調子を整える」食品、「栄養機能食品」では「カルシウム」を含む食品が多く利用されていた
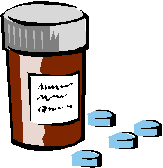 「特定保健用食品」で最も多く利用されていたのが「おなかの調子を整える」食品(404人)、次いで「コレステロールが高めの方へ」とする食品(271人)、以下「体脂肪が気になる方へ」とする食品(248人)
「ミネラルの吸収を助ける」食品(190人)の順に多く利用されていました。
「特定保健用食品」で最も多く利用されていたのが「おなかの調子を整える」食品(404人)、次いで「コレステロールが高めの方へ」とする食品(271人)、以下「体脂肪が気になる方へ」とする食品(248人)
「ミネラルの吸収を助ける」食品(190人)の順に多く利用されていました。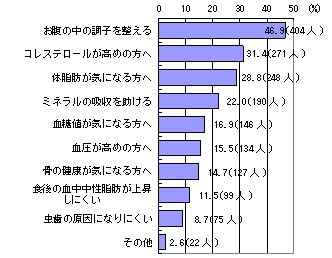
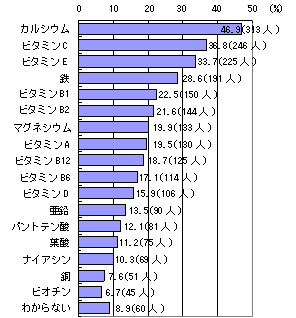
◆今後、保健機能食品を「利用したい」が「利用したくない」を少し上回った
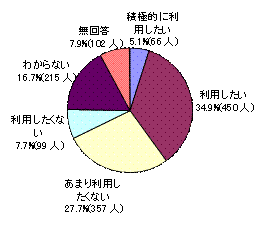
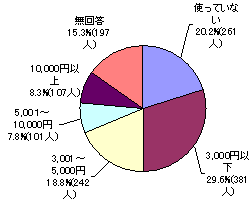
| バランスのとれた日常的な食事が基本 保健機能食品への正しい理解を |
消費者は、
「保健機能食品はあくまでも食品であり、医薬品のような効果は期待できない」ことなど、保健機能食品等に対して正しい理解を深め、過大な期待を抱かない心構えが必要です。 |
| 保健機能食品制度の改正 |
| 「保健機能食品制度」は、平成17年1月31日付で改正されました。(経過措置期間は平成18年3月31日) |
| 特定保健用食品制度の見直し |
従来の「特定保健用食品」に加え、
|
| 栄養機能食品制度の見直し |
|
| その他 |
| 保健機能食品に対し「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」の表示の義務付け |
| 詳しくは、厚生労働省ホームページより『「健康食品」に係る制度の見直しについて(医薬食品局通知)』参照 |